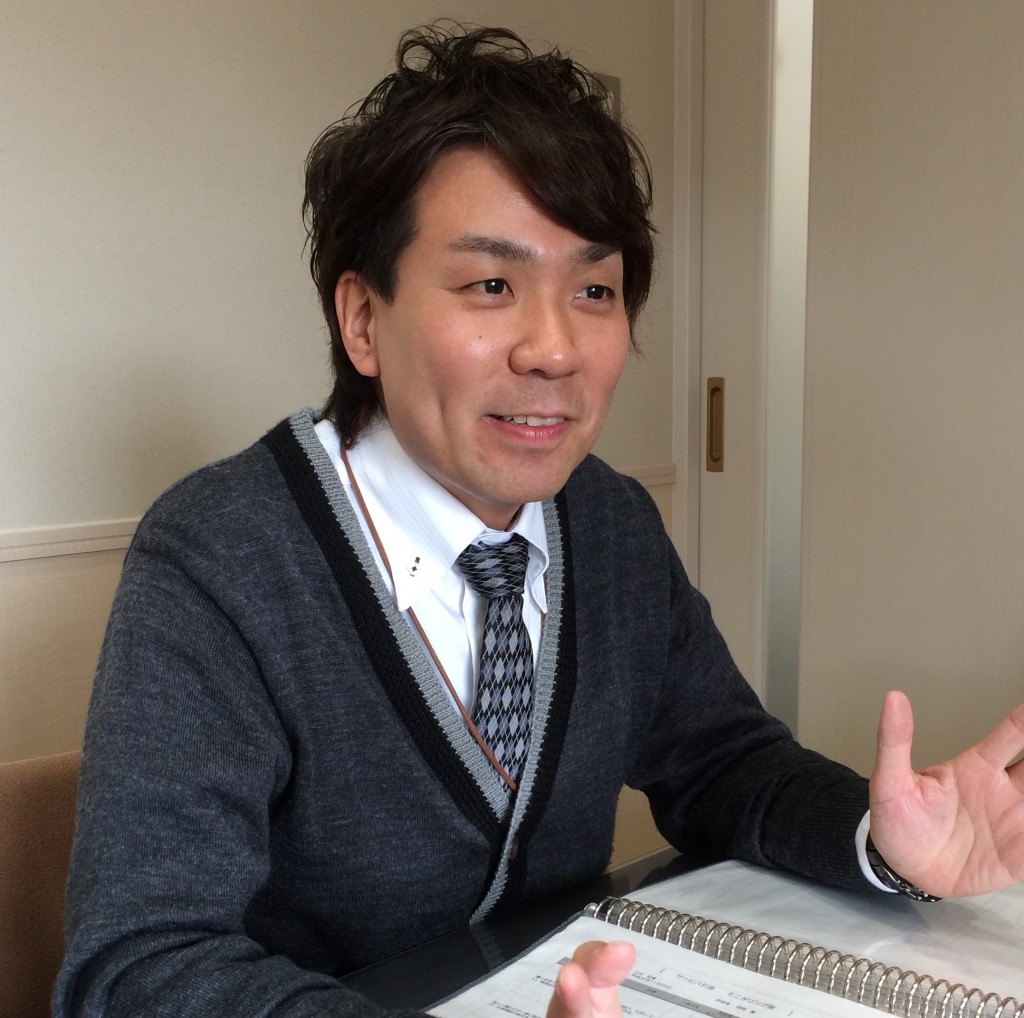毎日大変ですけど、そんな毎日もまた、貴重で、かけがえのないものと思います。
卒業生

菅原 貴矢 さん 法学部 法律学科
3年次編入(学士入学含む) 2019年卒業
関東在住 /会社員
- Profile
- ケーブルテレビ局の統括運営会社に勤務、商品企画本部でサポートサービスの企画開発を担当。
法律の知識を体系的に学びたいと法学部法律学科で学んでいらっしゃいます。
- 今の仕事に活かすため、いままで積み上げた知識の他に、必要な法律の知識を中心に学びたい ~法政大学通信教育部を選んだきっかけ~
-
ケーブルテレビ局の統括運営会社に勤務しています。入社以来、長年オペレーションに携わってきましたが、人事異動により現在は、商品企画本部でサポートサービスの企画開発を担当しています。
会社全体でワークライフバランス推進に取り組んでいます。具体的には残業削減、毎週水曜日のノー残業デーを徹底することで、その効果として、プライベートの時間が確保できるようになってきました。
空いた時間に自己研鑽をするのであれば、じっくりと時間をかけて大学で学ぶことが、自分の成長のためにもキャリアアップのためにもよいと考えていました。異動先の部署では、今まで積み上げた知識だけでは立ち行かないことがありましたので、いままで積み上げた知識の他に、商品開発に関係する法律の知識を学びたいと考え、法学部に決めました。
- 積極的に発言をしている受講者の存在がとてもよい刺激になりました ~学習について~
-
夏期スクーリングで「刑法総論」を受講しました。スクーリングの雰囲気ですが、受講者に頻繁に問いかけがありました。積極的に発言をしている受講者が多かったので、わたしも予習復習をがんばろうと、とてもよい刺激になりました。受講期間中に発言する機会に恵まれ、発言の際はとても緊張しましたが、発言後の安堵感はなんとも言えない、心地よいものがありました。
法学部でも他学部のスクーリングを受講できることを知り、マーケティングを扱った「経営学特講」を受講してみました。講義では基礎的な知識のほか、他社の最新事例をたくさん紹介していました。近い席の受講生たちとSWOT分析などのグループワークをする機会があり、スクーリングならではの醍醐味がありました。
現在、興味がある科目は、「保険法・海商法」です。こちらは通信学習で勉強する予定ですが、腹落ちするまでじっくりと勉強をしたいと思います。
- 自分のレベルに合った教科書、参考書を見つけることが、打開策につながる ~困ったこと、壁に当たったと感じたこと、その克服について~
-
入学して最初に学習をはじめたのは「民法総則」と「憲法」でした。法律についてまったくの無学だったので、テキストを読んでも正直なところ内容がまったく頭に入ってこなくて困りました。打開策として、行政書士のテキストを併読しながら勉強したところ、それがきっかけとなり、少しずつ繋がって理解が追いついてきました。自分のレベルに合った教科書、参考書を見つけることで、打開策につながることを体験しました。図書館を有効活用することで、自分のレベルに合う教科書、参考書に出会えると思います。
- 学習方法について(一問一答)
-
【1日の学習時間や時間帯は決めていますか?また時間の使い方で工夫していることはありますか?】
入学後、学生会を通じて学習方法について意見交換する機会が何度かありましたが、人それぞれだなぁと思っています。人それぞれ学習する環境が異なりますので、正解は一つではないと思います。自分にあった学習方法を作るのがよいと思います。
わたしの環境では、なかなかまとまった時間が確保できないのですが、通勤で30分ほど電車に乗っている時間がありますので、できるだけテキストを読む時間にあてています。昼休憩の時間もできるだけテキストを読む時間にあてています。少しずつでも、1ページだけでも読み進めて、学習を継続することが重要な気がしています。
個人的には一つの科目で行き詰ってしまい、学習の習慣が途切れてしまわないように、複数科目を並行して学習するのがよいのではないかと思っています。関連性が強い科目を同時に学習すれば効率よいですし、集中が途切れた時は、まったく関係ない科目に切り替えると気分転換になることもあります。
【リポートの書き方、単位修得試験対策で工夫していることはありますか?】
正直なところまだまだリポート作成は苦戦しています。改良の余地も多くあるため、具体的な対策をお話しできる段階ではないような気がしておりますが、リポートを書くにも、まずはテキストを読む必要があります。経験上、リポートを書きだすまでにはある程度時間をかけてテキストを読んで腹落ちしていないと、なかなか書きだすことができないようです。わたしの場合はあらかじめリポートの設題には目を通しておき、3、4科目を並行して学習しています。その中で、そろそろ設題のリポートが書けそうになったと感じた科目から、着手しています。
法学部のリポートは、条文、原則、例外、学説、判例、結論(自分の考え)を整理する必要があると思います。設題に記載のある参考文献すべてを揃えることは難しいですが、図書館を活用して必要な部分だけコピーをとっておくと、理解が深まり、リポート作成にも役立つと思います。
【単位修得試験について】
わたしの場合は単位修得試験の2週間前を直前期として考えています。直前期は6時までには起きて学習するようにしています。
シラバス・設題総覧に試験範囲が示されている場合があります。学習範囲を絞れますのでチェックしておくとよいと思います。
制限時間内に回答をまとめて、書く必要がありますので、書くことに慣れておくと試験でも慌てずに済むと思います。自分なりに設題を考えてみて、それに対する回答、構成を整理しておくと試験直前の確認に役立つと思います。試験直前に確認していた設題、回答案に近いものが単位修得試験にでたこともありますので、試験開始直前まで、あきらめずに、ぎりぎりまであがくのがよいと思います。
単位修得試験は同日で最大3科目まで受験が可能です。複数科目を受験できるように並行して勉強して、単位修得試験に間に合うように、リポート提出をする必要がありますが、2科目以上を同日に受験できれば、1科目がさっぱりわからなくても、もう1科目は回答できるかもしれません。効率的に単位修得試験で単位取得するにはよい方法ではないかと思います。
単位修得試験で回答の道筋が見えて、自分の言葉で書ききった時は、何とも言えない充実感と解放感があります。その日の晩酌は最高によい気分になります。
- 学生同士での情報交換や交流について
-
学生会には無理のない範囲で参加するようにしています。わたしは無口なほうですので話を聴くばかりですが、通信教育学部で学ぶ方は多様な方がいらっしゃいますので、こういった機会で交流することでよい刺激になり、自然と学習意欲が高まります。
趣味でジャズドラムを習っていますが、入学後、思い切って、ジャズ研究会サークルの見学を申し出ましたところ、こころよく参加を受け入れて下さいました。通学生の方、OB、OGの方、他大学の方々も一緒に、この時ばかりは勉強も仕事も忘れて、ジャズセッションを楽しむことができました。環境の変化により定期的なサークル参加はできない状況となりましたが、またいつか交流できればと考えています。
- これから、学びを志す皆さんへ
-

入学前は何年も勉強を続けることができるのか不安に思っていました。入学してから途中でやめるくらいなら、申し込むのをやめようかと、思ったこともあります。また40歳を前にして、いまさら大学に入学してまで勉強しなくてもよいのではないか、という意見もありました。
結果的には、わたしの中で入学してみたい想いが強く、やってみないとわからないという気持ちがありましたので、入学願書を取り寄せて、必要な書類を集め、説明会にも参加しました。その都度、自分の意思に変わりがないことを確認して、自分の意見を押して入学しました。
入学して1年がすぎました。足元では、やっぱり日々の仕事に疲れてしまい、勉強をはじめても睡魔に負けて、寝てしまうこともよくありますし、単位修得試験の直前期になると、試験に不安を感じて目が覚めて、朝はやくから勉強したりしています。それでも結果的に、単位取得の見込みがはずれてしまい凹んだりもします。プライベートの時間はなるべく勉強にあてて、試験直前まであがいて、あがいて、そんな毎日です。
それでも、あの時、思い切って入学してよかったなぁ、と思っています。
そんな毎日の繰り返しもまた、貴重で、自分にとっては、かけがえのない経験になっているものと思います。