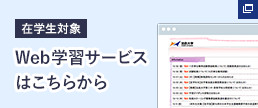よくあるご質問
学習について
テキスト・教材
- 入学前に通教テキストを読むことができますか。
全国各地の公共図書館等に授業科目の通教テキストを寄贈しています。
「法政大学通教文庫」設置場所一覧をご参照ください。
また、入学説明会会場では一部のテキストを閲覧することができます。- テキストはいつごろ届きますか。
補助教材・テキストの配本は、入学許可後、約2週間が目安です。
- どの科目のテキストが送付されますか。
入学手続き後、該当年次履修可能な科目(指定市販本採用科目および申告制通教テキスト科目除く)のテキストが送付されます。送付されない科目(指定市販本テキスト)は自身で購入してください。申告制通教テキストは大学へ申請してください。指定テキスト一覧は『通信学習設題総覧』に掲載しています。
- 教材が配本されたら、すぐ学習を始めてよいですか。履修登録等の手続きが必要ですか。
通信学習においては、履修登録は不要です。教材が届いたら、もしくは指定市販本を購入し、すぐにでも、テキストを読み始め、リポート作成を開始してください。
『学習のしおり』には、リポート提出締切一覧、試験登録締切一覧を掲載しています。
締切にあわせて、リポートを仕上げるように計画を立ててください。
- 進学手続後、テキストはいつごろ届きますか。
在学生に対し、新年度の『学習のしおり』『通信学習設題総覧』等の補助教材は毎年3月上旬に配本しています。通教テキストの配本は進学手続(新年度学費納入)後、約2~4週間が目安です。通教テキスト科目については3月に配本する『通信学習設題総覧』で確認してください。
- テキストが送付されてきましたが、自分が履修したい科目のテキストが入っていませんでした。
「指定市販本採用科目」、「申告制通教テキスト配本科目」、「履修可能対象外科目(学年や学科ごとのカリキュラムによる)」は配本されません。
「指定市販本」「申告制通教テキスト」の一覧は『通信学習設題総覧』(毎年3月上旬配本)でご 案内しています。- 「指定市販本」とはどういうものですか。
「指定市販本」とは市販されている本を大学がテキストとして指定している本のことです。
「指定市販本」に定められた科目は、大学からのテキスト配本は無く、一般の書店または本学生協書籍部で各自購入し、学習する必要があります。
「指定市販本」の一覧は『通信学習設題総覧』(毎年3月上旬配本)で生協書籍部通信販売価格(税込・送料込)を含めご案内しています。- 「申告制通教テキスト配本」とはどういうものですか。
各学科の「専門教育科目」の中で、学習を着手する時に申請して配本を受けるものが、申告制通教テキストです(所定の「申告制通教テキスト配本願」にて申請します)。
「申告制通教テキスト」の一覧は『通信学習設題総覧』(毎年3月上旬配本)でご案内しています。- 今月の『法政通信』がまだ届いていません。
毎月7日までに郵送されない場合は、前月号の『法政通信』(「共通欄」の前の項目)に記載されている発送元(業者)へ直接お問い合わせください。
なお『法政通信』は、通信教育部ホームページにも掲載していますので、利用してください。- シラバスを入手することはできますか。
WEBシラバスを公開しています。ご活用ください。
- リポートノートを使い切ってしまったので、再入手したいのですが。
リポートノートは販売となります。『学習のしおり』別冊とじ込みの「物品注文書」(こちらからのダウンロードも可能)で総務担当へ請求してください(定額小為替同封)。
物品 単位 価格 リポートノート(一般) 1組(5冊) 400円 リポートノート(地理調査法(自然編)) 1冊 400円 リポートノート(簿記Ⅰ・簿記Ⅱ) 各1冊 200円 - 補助教材(『学習のしおり』、『通信学習設題総覧』、『学科(学部)のしおり』)を紛失してしまったので、再入手したいのですが。
いずれも販売となります。『学習のしおり』別冊とじ込みの「物品注文書」(こちらからのダウンロードも可能)で総務担当へ請求してください(定額小為替同封)。
補助教材 価格 学習のしおり/設題総覧/経済学部のしおり 400円 法学部のしおり/日本文学科のしおり/史学科のしおり/地理学科のしおり 200円
科目
- 「基礎特講」と「総合特講」とはどのようにちがうのですか。
「基礎特講」は一般教育科目のその他の分野の科目になります。 1回のスクーリングで2単位修得となり、最大4単位まで卒業所要単位に算入します。「 総合特講」は専門選択科目の科目となり、1回のスクーリングで2単位修得となり、最大16単位まで卒業所要単位に算入します。
- 「公開科目」がどの科目か教えてください。
「公開科目」は開講する際にご連絡いたします。
主に、地方スクーリング、週末スクーリング、GWスクーリングやメディアスクーリングの開講科目が「公開科目」になる場合があります。- 専門科目は何から学習すればよいですか。
履修学年に達していれば、所属学部学科のカリキュラム上、どの科目から学習しても構いません。履修学年が低学年の必修科目は基本的なことを学ぶため、そちらを優先してすると良いでしょう。
- 履修科目の選択にあたり、科目の概要を知りたい。
科目の概要等を示したWEBシラバスを用意しています。
科目の選択時にご活用ください。毎年4月に更新します。
学習スケジュール
- 入学して数ヶ月たちますが、何からやってよいかわかりません。
「学習のしおり」の「学習について」の章を丁寧に読んでください。まず、自分が修得すべき科目を「教育課程表」で調べ、それぞれの科目がどのような内容であるかを「シラバス」を参考に、科目選択をしてください。
『法政通信』4月号・10月号には、新入生の方に対し、学習を始めるにあたって留意すべき点を記載しています。あわせてご一読ください。
さらに、学習の不安を解消するには、スクーリングに参加してみてはいかがでしょうか。中学・高校時代に得意だった科目からはじめてみてください。
また、Web通信学習相談制度も利用してみてください。卒業生が自身の体験をもとにアドバイスをくれます。- 翌年度の学事日程(スクーリングや単位修得試験の実施日等)は、いつ発表されますか。
例年、『法政通信』11月号で発表されます。
- 1年間で履修できるのは何単位までですか。
年間の修得単位は49単位です。49単位とは別に教職・資格科目を履修できます。
ただし、合計60単位までとします。年間スクーリング登録単位は49単位までとします。これには教職・資格科目を含みます。- どの科目を選んだらよいかわからないので、アドバイスがほしいのですが。
まずは通信教育部のシラバスや、配本されている通教テキストをめくったり、図書館等で指定市販本を入手し、とりかかりやすい(もしくは興味がもてる)内容かどうか確認してみることも一つの方法だと思います。
またWeb通信学習相談制度で卒業生に相談することもできます。- 教員にテキスト学習・リポート作成について質問をしたいのですが。
書面で質問ができる学習質疑制度があります。質問事項・調べた内容や方法・自分の見解について、記入例に従って作成し、郵送してください。
- 仕事をしているのですが、勉強時間はどのくらい確保したらよいでしょうか。
大学の授業は単位制度をとっており、1単位とは、通信学習では、テキストが約80ページで組まれていて、45時間をかけて学習することを意味します。
ですから、通常、4単位の科目を勉強していく場合、約320ページのテキストで180時間かけて学習することになります。- 3月卒業(9月卒業)を目指している場合、いつまでの単位が認められますか。
3月卒業:リポートと単位修得試験は1月受付実施分、スクーリングは冬期スクーリングまでになります。
9月卒業:リポートと単位修得試験は7月受付実施分、スクーリングは夏期スクーリングまでになります。- 科目等履修生ですが、年度内最後のリポート受付、単位修得試験はいつになりますか。
前期生:リポートと単位修得試験は1月受付実施分、スクーリングは冬期スクーリングまでになります。
後期生:リポートと単位修得試験は7月受付実施分、スクーリングは夏期スクーリングまでになります。- 自身の履修状況を確認したいです。
「Web学習サービス」で履修状況の確認が可能です。
3月末(後期生は9月末)にお送りする「履修・成績通知書」も参照してください。個人情報保護のため、お電話でのお問合せには回答できかねます。
Webでの確認が難しい場合には、ご自身が所属する学部担当宛てに書面にてお問合せください。
スクーリング
- 入学する時期によって受講できないスクーリングがありますか。
各スクーリングの申込締切日までに学籍がない方は申込できません。出願期間と初年度申込可能なスクーリングを事前にご確認のうえ、出願してください。出願期間はこちら。
- 入学後、すぐにスクーリングを受講しなければなりませんか。
卒業までの間に都合のよいスクーリングを受講し、卒業に必要な単位を修得してください。
- 履修計画を立てるため、年間のスクーリング予定を教えてください。
学部学科のカリキュラムにはスクーリングのみの開講科目があります。学部・学科一覧の「詳細を見る」をご参照ください。
また、通信学習で開講している科目が年度によってスクーリング開講科目としても履修可能となることがあります。
単年度ごとのスクーリング開講科目および開講日程は、WEB学習サービスInformation欄(2月上旬掲載)、「法政通信」毎年3月号・4月号でご案内しています。- 市ヶ谷キャンパスで開催されるスクーリングに参加することなく、卒業に必要な単位が取れますか。
【法学部生、経済学部生】は、メディアスクーリングの受講により、市ヶ谷キャンパスのスクーリングに参加することなく、卒業に必要なスクーリング単位(外国語科目2単位を除く)を修得することができます。
2年次・3年次編入学時において外国語科目が2単位以上認定される場合は、市ヶ谷キャンパスのスクーリングに参加することなく卒業することが可能となるケースがあります。
外国語科目(2単位)については、現在メディアスクーリングでは1単位のみ開講しているため、残り1単位分を市ヶ谷キャンパスの夏期・冬期もしくは春期・秋期スクーリング、地方スクーリング等に参加する必要があります。
【文学部生】は、卒業論文指導・外国語科目を含め、市ヶ谷キャンパスのスクーリングを受講する必要があります。
なお、メディアスクーリングを受講するためには、所定のPC利用環境を整える必要があります。ご自宅のPCでメディアスクーリングデモ画面の視聴が可能であるかを含めて、受講前にチェックしてください。- スクーリングで30単位を修得するためには、卒業までに何日くらい授業を受けなければならないのですか。
夏期・冬期スクーリングの場合は1週間で主に4単位分の授業を行いますので、最低でも卒業までの4年間に8週間分の受講が必要です(4単位×8週間=32単位)。1週間=6日間の授業です。よって、日数に換算すると、6日間×8週間=48日の受講が必要です。また、3日間集中のスクーリングや、メディアスクーリングと組み合わせることで、受講日数を圧縮することが可能です。目安として考えてください。
- 通学課程の開講科目を受講することができますか。
文学部日本文学科所属の通信教育部生は、通学課程開講科目の一部を春期スクーリングおよび秋期スクーリングとして受講できます。
開講科目は、「法政通信」4月号および10月号でお知らせします。- 東京スクーリング開講の際は、大学の近くに宿舎の用意がありますか。
本学市ヶ谷キャンパスで開講する夏期および冬期スクーリング時に、宿舎の紹介をしています。
宿舎については、「法政通信」5月号および11月号でお知らせします。
また、旅行手配を行う学内店舗を利用することも可能です。- 夏・冬期スクーリングの受講許可・不許可はいつ分かりますか。
スクーリングによって異なります。各スクーリングの様々な日程詳細はスクーリングごとに「法政通信」等でご案内します。
- スクーリングは必ず受講しなければいけないのですか。
本学を卒業するためには所定の卒業所要単位を修得することが必要で、卒業所要単位のうち、スクーリングで修得しなければならない単位数が定められています。
- 春期・秋期スクーリングの授業はどのように行われますか。
春期は4月~7月、秋期は9月~1月の間、毎週1回の授業が夜間の時間帯に開講されます。
- スクーリングで、「英語」をとりたいと考えています。「総合外国語特講」と「英語」のどちらが簡単ですか。
「英語」は教養教育科目であり、「総合外国語特講」は専門教育科目です。
教養課程で「外国語」は必修となりますが、「総合外国語特講」は選択科目です。
講義内容はスクーリング毎に異なりますが、「英語」の方が基本的な内容となります。- 夏期・冬期スクーリングの英語は、どのような授業でしょうか。
授業によって、会話中心であったり、文法中心であったりします。
詳細はその都度、シラバスを見て確認してください。- 夏期・冬期スクーリングの受講科目を確認したいのですが。
受講申込受付期間終了後、2週間程度たちましたらWEB学習サービス上で確認できます。
- 「他学部・他学科公開科目」はどの学部の科目でも好きな科目をスクーリングで修得すれば卒業所要単位となるということですか。
「公開科目」として開講される科目は、地方・メディア・週末・ゴールデンウィークスクーリングで開講される科目に限られます。履修学年は主に2~4年次を対象とし、卒業所要単位として8科目16単位まで履修することができます。
- スクーリングに書かれている「参考書」を購入する必要はありますか。
参考書は任意です。必要に応じて入手してください。
- 春期・秋期スクーリングだけで、卒業に必要なスクーリング単位を取得できますか。
春期・秋期スクーリングの開講科目は、主にスクーリング必修科目を中心に開講されています。
地方スクーリング、週末スクーリング、GWスクーリングやメディアスクーリングも開講科目が限られています。
これらのスクーリングの受講だけで全てのスクーリング単位を修得するのは非常に難しいと思います。
夏期・冬期のスクーリングをあわせて受講する必要があります。- 各スクーリングの受講申請手続きはいつから始まりますか。
各スクーリングの開催に関するお知らせは「法政通信」でご案内します。
毎年「法政通信」2月号・3月号・4月号では、全スクーリング日程およびスクーリング詳細の掲載号一覧を発表しています。
おおそよ各スクーリング開催月の2ヵ月前の「法政通信」で受講申請手続きのご案内をしています。- 地方スクーリングの授業はどのように行われますか。
全国各地の地方都市(札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡)で土日祝日などを利用して、3日間連続の集中形式で授業を実施します。
- メディアスクーリングの授業はどのように行われますか。
法政大学のメディアスクーリングでは、「オンデマンド方式」のスクーリングを開講しています。PCを利用して授業を受けた後に単位修得試験を受験し、合格すれば単位が修得できます(一部リポート試験の科目もあります)。
メディアスクーリングで受講できる科目一覧や、各科目のシラバス、講義のデモ画面は、こちらからご覧いただけます。- 科目等履修生でもスクーリングの受講ができますか。
スクーリングの受講は可能です。ただし、受講できる科目に制限があります。科目等履修生が受講できるスクーリング科目については、WEB学習サービスInformation欄2月上旬、「法政通信」3月号4月号に掲載します。
- スクーリング受講料を支払ったあと、仕事の都合で出席できなくなった場合、受講を辞退することはできますか。
一旦納入された受講料は返金しませんが、やむを得ない事由で登録科目の受講ができなくなった場合は原則として、授業開始1週間前に受講辞退の届出をすることで受講料を返金します。詳細は各期のスクーリング手続きが掲載された「法政通信」で確認してください。
- 文学部地理学科の現地研究とはどういうスクーリングですか。
現地研究の日程・実施場所および概要は例年「法政通信」5月号・10月号で発表しています。
- 春期・夏期・秋期・冬期のスクーリングには抽選がある科目と抽選のない科目がありますが、受講の申請方法に違いはありますか。
2018年度から、抽選のあり・なしにかかわらず各スクーリングで「履修申請」を行う方式になりました。
毎年、法政通信の次の号でお知らせしています。
春期スクーリングは「法政通信」2月号
夏期スクーリングは「法政通信」5月号
秋期スクーリングは「法政通信」7・8月号
冬期スクーリングは「法政通信」10月号
リポート
- リポートの書き方について、参考になる書籍を紹介してください。
主に通学課程向けに作成している本学の学習支援ハンドブックの中で、「リポートの書き方」について分かりやすくまとめています。通教生も参考にしてください。また、法政大学懸賞論文のWEBサイトでは、論文の書き方に役立つ書籍を紹介しています。通信学習の成果をはかるためにも、在学中に法政大学懸賞論文に応募してみてはいかがでしょうか。
- リポートの作成の際にワープロ(パソコン)を使用してもいいですか。
『設題総覧』各科目の〔特記事項〕に指定がない場合は、基本的に、ワープロ(パソコン)使用可能です。
- リポートの記述字数はどのくらいですか。
『設題総覧』各科目の〔特記事項〕に指定がない場合は、基本的に、1設題につき2,000字程度です。
- リポートノートはどのようなものですか。
大学指定の提出用のリポートノートです。
2設題(4単位構成科目)用と1設題(2単位構成科目)用の2種類のリポートノートがあります。- リポートの1科目につき、設題数はどのくらいですか。
4単位科目では2設題(一部4設題)、2単位科目では1設題(一部2設題)です。
- リポートは何回まで提出できますか。
リポートは1設題につき年間3回まで提出できます。
- リポートが返却(教員添削)されるまでにどのくらいの期間がかかりますか。
リポートは提出締切日から2ヶ月程度で返送されますが、科目によってはそれ以上かかる場合もあります。
- どの科目のリポートから提出すればよいですか。
科目の履修の順番に定めはありません。
各自でカリキュラムを確認し、履修可能な科目から順次リポートを提出してください。ただし、履修可能学年は科目ごとに定められています。- 提出したリポートが合格して、その評価が低かった場合、再度提出することはできますか。
一度合格した科目のリポートを再度提出することはできません。
- 『設題総覧』に設題が掲載されていない科目があるのですが、リポートの提出方法を教えてください。
外国語科目と「地理調査法(自然編)」および「簿記Ⅰ」、「簿記Ⅱ」、「簿記Ⅲ」、「簿記Ⅳ」の科目は別刷の専用リポートノートになります。
設題はリポートノートに印刷されていますので、そちらに解答し提出してください。- 旧テキストでリポートを提出したのですが、新テキストに移行した場合、リポートは出し直す必要がありますか。
旧テキストでのリポート評価が有効ですので、評価が合格であった場合は出し直す必要はありませんが、評価が再提出であった場合は旧テキストで学習し、旧テキストの経過措置期間(2年間)内に再提出するようにしてください。
経過措置期間内にリポートが合格しなかった場合は、新テキストの設題で再提出することになります。- スクーリングで先に2単位修得し、不足単位を通信で修得する場合、リポートはどの設題を提出すればよいですか。
リポート設題が2設題の科目は「第1回(1)」、4設題の科目は「第1回(1)(2)」を必ず提出してください。この場合、単位修得試験は2単位試験を受験することになります。
2013年度のカリキュラム変更に伴い、4単位から2単位ずつ2科目に変更した科目の場合(例:2012年度まで「経営学」、2013年度から「経営学総論Ⅰ」「経営学総論Ⅱ」)、2012年度末までにスクーリングで2単位を修得済みで、なおかつ残り2単位をリポート等で履修途中の場合、経過措置期間中はリポートは再提出中の設題を提出してください。
また、単位修得試験は、2012年度までの旧科目名の試験問題を解答してください。
ただし、受験票には新科目名で表記されますので、試験問題冊子に記載されている注意事項を確認してください。
本件など、わからない場合は事前に事務課に問い合わせてください。- リポートを再提出したいのですが、前回のリポートを紛失してしまいました。
前回のリポートを紛失して添付できない場合は、再提出リポートの「リポート表紙」にその旨を明記し、新年度設題で解答、提出してください。
- 再提出リポートはいつまでに提出すればよいですか。
再提出リポートの提出期限は新規提出年度を含めて3年間(年度)です。
再提出評価を受けたリポートにそのリポートの再提出期限を明記しますので、その年度までに合格するようにしてください。- 再提出期限までにリポートが合格できなかった場合、以後の再提出はできないのですか。
期限までに合格できなかった場合は、再提出リポートの「リポート表紙」にその旨を明記し、新年度の設題で解答し、再提出リポートとして提出してください(この場合、前回のリポートを添付する必要はありません)。
その後の再提出期間は2年間(年度)となります。- リポートが再提出評価ですが、旧テキスト(自分が学習しているテキスト)の移行経過措置期間が終了してしまった場合、どうすればよいですか。
テキストの経過措置期間内に合格できなかった場合は、再提出リポートの「リポート表紙」にその旨を明記し、新年度の設題で解答し、再提出リポートとして提出してください(この場合、前回のリポートを添付する必要はありません)。
その後の再提出期間は2年間(年度)となります。
ただし、カリキュラム変更により変更した科目は、経過措置期間中に単位を修得できない場合は、学習履歴が無効となります。- 一度合格したリポートの評価はいつまで有効ですか。
学籍が継続している限り有効です。
- リポート等を郵送する場合、郵便料金の割引はありますか。
リポートの提出・返送、学習質疑、卒業論文の提出に限り「第4種郵便物」の取扱いが受けられます。
1通100gまで15円、100g増すごとに10円追加で送ることができます。
単位修得試験
- 単位修得試験について教えてください。
リポートを提出すると単位修得のための科目試験が受験できます。本学ではこの試験のことを単位修得試験と呼んでおり、全国約20都市で年8回日曜日に実施しています。全日程・全会場で全学科の全科目の試験を3科目まで受験することが出来ます。単位を修得するためには、リポートと単位修得試験の両方に合格することが必要となります。
- 単位修得試験はどこで受験できますか。
全国約20都市で同時に実施します。事前に登録する際には、全国の会場から選択できます。WEB学習サービスから受験申込が可能です。
- 単位修得試験の試験時間を教えてください。
10:00より試験監督が受験上の注意などの説明を開始します。
1科目め 10:20~11:20
2科目め 11:20~12:20
3科目め 12:20~13:20- 単位修得試験の受験資格について教えてください。
試験登録締切日以前に、受験したい科目および単位について決められた設題数(4単位試験受験の場合は全設題)のリポートを提出して、試験登録をすることが要件です。
リポートの合否は受験資格には関係ありません。
必要な設題数のリポートが提出され、試験登録をすれば受験することができます。- 単位修得試験はどのような出題がされますか。
試験は基本的に論述式です。原則として辞書やテキスト、参考書等は参照不可となります。
- 単位修得試験の出題範囲は受験前に公表されますか。
毎年3月に年度を切り替えて配本する「通信学習設題総覧」で単位修得試験の出題範囲を公表しています。 公表がない科目は、テキスト全体を出題範囲としています。
- 1回の単位修得試験で何科目受験できますか。
1回の試験では、最大3科目まで受験できます。試験月によって受験できない科目は発生しません。例外として、前期メディアスクーリング試験は6および7月、後期メディアスクーリング試験は12月および1月に実施します。
- 試験の過去問題を入手することはできますか。
過年度を含め、単位修得試験問題(過去問題)の公開・販売・閲覧等は一切行っておりません。
ただし、単位修得試験会場で自分が使用した問題冊子は持ち帰ることが出来ます。- 構成単位4単位の科目の単位修得試験の登録では、2単位試験と4単位試験を選択できますが、どちらを登録すればよいですか。
2単位と4単位の別がある科目について「2単位」試験を選択できるのは次の2つのケースに限定されます。
以前にスクーリングを受講しスクーリング試験に合格し、スクーリング単位の2単位を既に修得している場合、もしくは、編入生が認定・換算後の不足単位を2単位受験する場合です。
また、第1回目のレポートを提出していることが条件です。- 前回受験した単位修得試験の結果が判明していませんが、今回の試験で連続して同一科目を受験できますか。
試験結果が判明する前に同じ科目を連続して受験することは可能です。
なお、試験結果が発送されるのは試験日より約50日後ですので、それより前に次回の試験登録締切日が到来することがあります。前回の試験結果を受け取ってからでは次回の試験登録締切日に間に合わないことが多いので、よく検討して試験登録を行ってください。
また、受験票が届いた後に試験結果が分かる場合があります。
合格済の科目は受験できません。したがって、全科目合格の場合は、受験会場に来る必要がなくなります。- 試験登録締切後に科目や受験会場を変更することはできますか。
試験登録締切後の受験科目の変更は一切認められません。
受験会場の変更は、地方会場から東京会場(本学市ヶ谷キャンパス)へ変更する場合に限り認めています。- 試験の評価基準を教えてください。
単位修得試験の評価基準はこちらをご参照ください。
- 試験が合格した場合で、さらに高評価の成績を取りたい場合は、再度受験することはできますか。
できません。
- テキストが新テキストに移行した場合、旧テキストに対応する試験問題は出題されますか。
旧テキストの移行経過措置期間(2年間)内は旧テキストに対応する試験問題も出題されます。経過措置期間後は旧テキストに対応する試験問題は出題されませんので、新テキストを学習し、新テキストに対応する試験問題を解答することになります。
- 単位修得試験の試験問題で、科目名の前に「指」、「新」、「旧」と記載されていますが、どれを解答すればよいですか。
同一科目で新・旧テキスト・指定市販本の教材の別がある場合に記載しています。
この場合は、自分が学習したテキストに該当する問題を解答してください。- 試験の採点基準や採点内容を教えてください。
実際の点数や採点基準は公表されません。
また、採点の内容についての疑問や照会、異議、各科目の合格率に関する問い合わせ等には一切応じられません。- 翌年度4月以降の単位修得試験日はいつ、どのように発表になりますか。
法政通信11月号に翌年度の「通信教育部学事日程」を掲載し、その中で、単位修得試験日をお知らせいたします。
卒業論文
- 卒業論文を作成するにあたって疑問点が出てきた場合、どうやって先生に質問すればよいですか。
卒業論文指導を受けるときに直接質問することが可能ですが、それ以外の場合は「卒業論文学習質疑」を各学部宛に提出してください。
担当教員から回答いたします。担当教員によっては、別途資料の提出を求めることがあります。- 卒業論文の論題の決め方が分からないのですが、どうすればよいですか。
興味のある分野、さらに研究してみたい科目などを検討してみてはいかがでしょうか。
夏期・冬期スクーリング期間中に実施する、卒業論文一般指導の受講もしてみてください。- 卒業生の卒業論文を閲覧することはできますか。
文学部地理学科以外は、卒業論文の閲覧は行っておりません。
- 卒業生の卒業論文のテーマを知ることができますか。
毎年「法政通信」6月号は卒業生記念特集ページを用意しています。卒業論文のテーマ、メッセージ、お住まいの都道府県を卒業生の希望により掲載しています。ぜひ参考にしてください。
- 卒業論文一般指導に出席する際、予約は必要ですか。
予約の必要はありません。当日決められた時間に受講してください。
- 文学部の卒業論文第3次指導は何学科にあるのですか。
史学科と地理学科で実施します。こちらの指導は文書指導になります。
- 経済学部の卒業論文計画書指導ではどのような指導が行われますか。
卒業論文のテーマ設定や内容・構成などを提示していただき、それに対し担当教員が指導を行います(文書指導)。
- 経済学部の卒業論文計画書指導の受講後、卒業論文のテーマを変更したい場合はどうすればよいですか。
「卒業論文学習質疑」を経済学部宛に提出してください。
担当教員から回答していただきます。大幅な変更で科目・担当教員が変更となる場合は、計画書指導からやり直しとなります。- 卒業論文の面接試問日はいつごろ発表されますか。また日程を指定することはできますか。
面接試問の日程は、卒業論文提出からおよそ1週間後に文書でお知らせします。
日程は夏期・冬期スクーリング期間中の半日が設定されますが、日程の指定や変更はできませんのでご了承ください。- 卒業論文の面接試問ではどのようなことを聞かれますか。また必要な物はありますか。
面接試問では、卒業論文に関連した内容を聞かれます。
そのため提出された卒業論文のコピーや参考文献を持参することをお勧めします。- 卒業論文は第4種郵便に入りますか。
卒業論文は「学習のしおり」に書かれているように第4種郵便物に該当しますが、郵便事故に対応できるよう「配達記録」または「簡易書留」便を使用してください。
- 卒業論文の合格率など教えてください。
卒業論文の合格率、不合格率は公表しておりません。
しかし、不合格になる可能性はありますので、十分な時間をかけて、卒業論文を作成してください。- 卒業論文面接試問とスクーリングの授業が重なってしまいました。どうしたらよろしいでしょうか。
申し訳ありませんが、スクーリングは欠席していただき、卒業論文面接試問の方を優先してください。
- 卒業論文面接試問の所要時間はどのくらいですか。
平均20~30分ですが、所要時間は人によって異なります。
- 「卒業論文提出申請書」兼「年度途中卒業希望書」の提出時期はいつですか。
『法政通信』3月号・9月号を参照してください。
- 卒業論文提出申請書に書いた卒業論文の論題から変更することは認められますか。
法学部:変更してかまいません。卒業申請書は仮の論題を書いていただいて大丈夫です。
文学部:変更できません。変更する場合は、第1次指導からやり直しとなります。
経済学部:変更できません。変更する場合は、計画書指導からやり直しとなります。- 卒業論文提出申請をしたが、論文提出締切日までに論文の作成が間に合いそうにない。どうしたらよいですか。
卒業論文提出締切日までに、「卒業論文提出申請取消願」を提出してください。
記入例は『法政通信』に掲載されています。